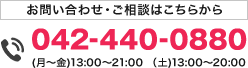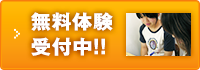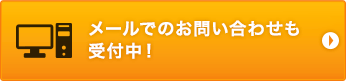専修大学過去問題分析 国語編
2018.10.20

専修大学国語入学試験の分析です。
大問は3問構成、全問選択問題で、試験時間は60分です。
2018年の全学部入試問題を参照すると、下記のような形式で出題されていました。
大問1:読解問題 (現代文)(8問)
大問2:読解問題 (古文)(8問)
大問3:語彙・知識問題 (5問)
◎問題構成の内容
〇大問1 (8問)
出典:『読書と日本人』津野海太郎
現代文はここ数年、評論文が出題文となっております。
出題文の内容は社会問題に焦点をあてたものや、日本における社会習慣に対する考察をテーマとしたものが多いようです。文章量はセンター試験よりも少し短くまとまっている程度です。
設問の傾向としては、
・出題文中の漢字に関する問題(3題)
・出題文中の空欄に補充する適語を選ぶ問題(2題)
・内容一致問題(3題)
となっています。
漢字に関する問題は漢字そのものを問うのではなく、その漢字と熟語となる(もしくはならない)ものを選んだり、その語の反意語・同意語を選んだりする問題が中心になっています。
また、ここ2年間ほどで増えているのが、「当てはまる(当てはまらない)ものがいくつあるか」を答えさせる解答形式です。正しいものが1つとは限定できず、消去法が使えない解答形式のため全選択肢を検討する必要があり、解答に時間を使わざるをえません。時間との戦いが以前よりも少し厳しくなっているため、気を付けたいところです。
〇大問2 (8問)
出典:『十訓抄』
古文は幅広く様々な文献から出題されていますが、説話・日記文学からの出題が比較的多いようです。出題内容は標準的な内容のものが多く、教科書レベルやセンター試験向けの標準的な参考書で対応できるレベルの問題が中心となっています。
設問の傾向は、
・語彙問題(2題)
・文法的説明問題(2題)
・内容一致問題(4題)
となっています。
文法的説明では、主に語句の品詞や動作の主体を答える問題が出題されています。
〇大問3 (5問)
国語の知識を問う問題です。
設問としては主に、
・四字熟語に関連する問題
・ことわざに関連する問題
・口語の文法問題
・文学史
が出題されます。
それぞれを完璧に習得しようとするとかなりの時間と労力が必要となります。時間がない場合は、漢字や読解の練習をしながら、出てきた作品・表現などを逐一チェックして覚えていく習慣をつけましょう。
◎対策
〇選択肢の検討が多いため、現代文は論理的に読む癖を!
ここ数年で選択肢を検討する要素が増加傾向にあるため、時間の使い方が少し難しくなっています。選択肢を見たときに「なんとなく」正しそう(間違ってそう)と感じることはあると思いますが、それだけにこだわらず、出題文に根拠を求めるようにしていきましょう。そうすることで、後ほど解答に迷いが生じ、余計に時間を割いてしまうリスクを減らすことができます。
〇古文を得点源にしよう!
現代文・古文ともに問題の難易度としては極端に高いことはないと感じます。
特に古文については設問の方も現代文より素直で、しっかりと根拠を押さえられれば安定して得点することも可能でしょう。
古文の読解練習をする際には単語の意味をしっかり押さえることと、動作の主体を常に意識しながら読み進めることを忘れずに!
具体的に入試を受けるにはどの程度の点数をとればいいのか、また、自分の実力だとどのくらいの点数がとれるのか……などなど、詳しい情報や個人的な分析に関しましては、当教室までお問い合わせください。