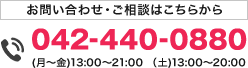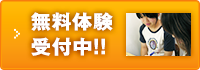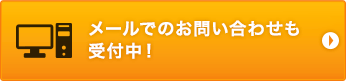駒澤大学過去問題(全学部統一)分析 国語編
2018.10.10

駒澤大学国語入学試験の分析です。
大問は3問構成、全問選択問題で、試験時間は60分です。
2018年の全学部入試問題を参照すると、下記のような形式で出題されていました。
大問1:漢字問題 (8問)
大問2:読解問題 (現代文)(9問)
大問3:読解問題 (古文)(8問)
◎問題構成の内容
〇大問1 (8問)
漢字問題は2つの形式に分かれます。
1つは傍線部で示されたカタカナに当てはまる漢字を選択肢から選ぶ形式、もう1つは傍線部で示されたカタカナに当てはまる漢字と同じ漢字を含んだフレーズを選択肢から選ぶ形式です。
どちらも基礎的な漢字の知識を持っていれば解けるレベルと考えられます。日頃から練習を重ね、確実に得点できるようにしましょう。
〇大問2 (9問)
出典:源了圓『型』(創文社)
ここ3年以上は評論の文章の出題が続いています。
文章量は極端に多いわけではなく、難易度も概ね標準的です。
近年の傾向として、設問の内容は、
・本文中の空欄に適する語句を選ぶ(5~6題)
・本文から抜き出した一文を挿入するのに適した場所を選ぶ(0~1題)
・本文および傍線部の内容に合致する選択肢を選ぶ(1~2題)
・文学史問題(0~1題)
に分けることができます。
特徴として、本文中の空欄に適する語句を選ぶ問題が多く、文脈や論理の流れを追う力を問われているように感じます。
〇大問3 (8問)
出典:『十訓抄』
古文の問題は幅広い文献からの出題がされています。
近年の設問の傾向は、
・傍線部の単語や文章の意味として正しいものを選ぶ(3~4題)
・傍線部や本文の内容として正しいものを選ぶ(2題)
・傍線部の品詞分解、文法的説明から正しいものを選ぶ(1題)
・傍線部の動詞に対して正しい主語を選ぶ(0~1題)
・本文の空欄に当てはまる語句を選ぶ(0~1題)
・文学史問題(1題)
となっています。
語句や文章の意味および文中での使われ方を中心に問題が構成されています。主語を聞いたり、品詞分解をさせたりする設問もあるので、文法もないがしろにはできません。
◎対策
〇奇をてらった問題は少ないため、落とさないことが重要
全体として問題の構成も設問の内容も素直な編成です。そのため、取れる問題を確実に取っていくことが最重要になってきます。
現代文・古文の大問には様々な種類の問題があるので、順番にこだわらず、自分が解けるものから解答を決めていきましょう。また、漢字は1問も落とさないように練習をしましょう。
〇内容の把握は重要、意味も踏まえて正しく押さえる
国語の入試ですので、当然のことながら本文の内容を問う問題が重要になってきます。
現代文・古文のいずれも語句の意味や内容を問う問題が出てくるので、全体的な文章のテーマや、各段落で語られている内容を押さえながら解きましょう。また、特に現代文では空所補充の問題が多いため、文脈を理解すること、それぞれのキーワードが作者にとって肯定的もしくは否定的にとらえられているのかの判断をしておくことが大事になるでしょう。
文学史は出ても1~2問です。もしここに集中して時間を割く余裕がなければ、読解の練習をする傍らで少しずつ覚えていくと得点できる可能性は上昇するでしょう。
具体的に入試を受けるにはどの程度の点数をとればいいのか、また、自分の実力だとどのくらいの点数がとれるのか……などなど、詳しい情報や個人的な分析に関しましては、当教室までお問い合わせください。