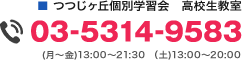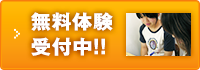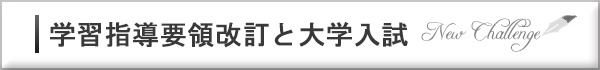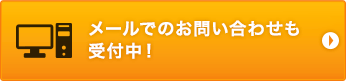変貌を遂げた総合型選抜入試と学校推薦型選抜
~その実態と対策~
大学受験はここ数年で大きくその様相を変え、私立大学のみならず国公立大学でも一般選抜に加えて学校推薦型選抜、総合型選抜を活用する大学が増えてきました。
2010年度は入学者数における一般選抜と推薦(現学校推薦型)・AO(現総合型選抜)の割合は33.1%だったのに対して、2013年の調査では学校推薦型・総合型選抜の割合が43.5%となり(私立大学に限っては52.4%)、2022年度は49.7%(同じく57.4%)となっております。今後この数字はますます大きくなっていくと予想されます。
大学の入学者数、すなわち定員は増えることはないので、学校推薦型・総合型選抜での入学者が増えることは一般選抜での合格者が少なくなっていくことを意味します。
これからの大学受験(特に私立大学受験)は一般選抜だけでなく、学校推薦型・総合型選抜での入学も視野に入れた学習をしていく必要があるでしょう。
【目次】このページの内容は以下の通りです。
現行の試験対策は「2. 2020年度以降の総合型選抜入試・学校推薦型選抜入試」をご覧ください。
1.2019年度までのAO・推薦(旧制度)
1-1.AO入試について
1-2.推薦入試について
1-2-1.指定校推薦入試
1-2-2.公募推薦入試
2.2020年度以降の総合型選抜入試・学校推薦型推薦入試(現行制度)
2-1.名称の変化
2-2.学力試験の義務化
2-3.試験実施時期の変更
2-4.まとめ
3.当塾での対策
3-1.現行試験への対策
3-1-1.当塾の定期試験対策
3-1-2.当塾の小論文対策
3-1-3.当塾の志望理由書対策
3-1-4.当塾の面接対策
3-2.新試験への対策
2020年度から始まった入試改革も間もなくピリオドを迎えようとしています。入試がどのように変わったのか、また変わった入試にどう対処していくべきかお悩みの方が多いでしょう。 現行の入試と当塾での対策について、総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試に焦点を当ててまとめました。
1.2019年度までのAO・推薦
昨今の大学入試において学生の半数(平成29年度のAO入試・推薦入試での大学入学者が、全体の44.3%で過去最多となりました)がAO入試や推薦入試で入学するというデータからも分かるように、いまや一般入試で大学へ行くのが当たり前とは言いにくくなってしまいました。自分が学生だった頃はこの制度は主流じゃなかった、とお思いの保護者の方もいらっしゃると思います。現行制度における推薦入試とAO入試との違い、そして対策をまとめました。
1-1.AO入試について
出願 → 書類審査 → 小論文・面接・ディスカッションなど
出願に際して学校長などの推薦が必須となりません。生徒が自身でエントリーシート(志望理由書)を作成し、出身学校の調査書などと合わせて書類審査となります。書類審査通過後は一般的には小論文や面接を課す大学が多いようですが、近年はグループワークやディスカッションなど対話型の課題を課す大学もあります。
AO入試で最も重要なポイントは、「自分がいかにその大学に相応しいか」をアピールすることです。大学の学部にはそれぞれアドミッションポリシー(その学部が求める理想の学生)が設定されており、AO入試ではそれを満たす生徒を選抜する制度です。学科試験がほとんどの大学で課されないので一見難易度は低いように見えますが、①将来へのビジョン ②①に対する現在の取り組み ③その大学でなければならない理由 が考慮されますので、早い段階からの準備が必要となってきます。また近年英語外部試験(実用英語技能検定やTOEICなど)やその他の資格が出願の必須要件になっている大学もあります。
| 推薦者 | 定員 | 実施時期 | 重視される点 | 学力 |
| 学校長に限らず | 大学によって異なる | 8~2月 | 人物、将来へのビジョン | 評定平均、資格等 |
1-2.推薦入試について
一口に推薦入試と言っても、その中身は指定校推薦、公募推薦(一般推薦、スポーツ推薦など)、自己推薦、などがあります。
推薦型入試では学科試験のウェイトが低い(学科試験が課されない大学もある)代わりに、高校での成績が評価されます。いわゆる内申点というものですね。多くの大学では高1の1学期~高3の1学期までの成績の平均が基準となります(評定平均)。即ち、高3から受験を意識しても間に合わない場合があります。
そしてAO入試と同様に、英語外部試験の一定の成績やその他の資格が出願用件であったり、成績を活用することで、必要な評定平均が下がる大学もあります。
1-2-1.指定校推薦入試
高校での選考 → 出願 → 小論文・面接など
指定校推薦は、高校で選抜された生徒のみがその大学への出願権を得られるものであり、高校における選抜を通過するとほぼ確実に合格ができます。故に、校内選抜の競争が熾烈なものとなります。また、高校自体が自分の行きたい大学(学部・学科)への指定校推薦の権利を持っているか、ということが重要になります。多くの高校では8~9月に指定校の発表があるようです。この入試形態では各大学に対して定員がほぼ1名と、非常に狭き門となっております。評定平均も4.0以上が求められる場合も多く、高校入学時から成績を保たねばなりません。
| 推薦者 | 定員 | 実施時期 | 重視される点 | 学力 |
| 学校長 | 大学ごとに各高校から ほぼ1名 |
校内選考:8月~ 出願:9月~ |
学校での活動や ボランティア等 |
評定平均、資格等 |
1-2-2.公募推薦入試
学校長からの推薦 → 出願 → 書類選考 → 小論文・面接・実技試験など
公募推薦入試は一般推薦・スポーツ推薦・技能推薦・自己推薦などに分かれます。このうち自己推薦入試は学校長の推薦を必要としないため、AO入試に近いものです。書類選考後は一般推薦では面接や小論文、スポーツ・技能推薦では面接や実技が課されます。
| 推薦者 | 定員 | 実施時期 | 重視される点 | 学力 |
| 学校長 | 大学によって異なる | 10月~11月 | 学校での活動や ボランティア等 |
評定平均、学科試験、 実技、資格等 |
2.2020年度以降の総合型選抜入試・学校推薦型選抜入試
2-1.名称の変化
2020年度より
AO入試 ⇒ 総合型選抜入試
推薦入試 ⇒ 学校推薦型選抜入試
に名称が変わります。
2-2.学力試験の義務化
従来のAO入試・推薦入試ではほとんど必要とされていなかった「学力評価」が義務化されています。一般選抜入試以外は試験日程の関係で合格から入学までズレがあり、入学者の学力の低さが問題とされてきました。新入試では全入学希望者に学力テストを実施することで入学前の学力を担保する狙いです。
大学が学生の学力の判断材料として独自の問題を使うのか、大学入学共通テストを使うのかで難易度が変わってきます。前者なら大学が難易度を調整することができるので、極端に言えば漢字の書き取りやアルファベットを書く、というようなものでも出題できてしまいます。後者は大学入学共通テスト(旧センター試験)を用いるものです。現行入試でも一部国立大学では共通テストを受験し、一定のスコアを獲得することを要件にしているところもあります。
大学入学共通テストは2025年度から情報Ⅰの新設や社会の科目の再編により、難易度が高くなることが予想されます。
付け焼刃の勉強では通用しないでしょう。
私立大学においては現状では小論文を課す大学が多いようです。
2-3.試験実施時期の変更
旧来のAO入試では実施時期が8~2月、推薦入試では10~11月ですが、現行の総合型選抜入試は9月~、学校推薦型選抜入試は11月~と遅くなっています。
2-4.まとめ
旧来のAO入試や推薦入試は一部大学では「一般入試より楽」「大学入学を早く決めたい」「ギリギリになってからでも間に合う」ような、一般試験を突破する学力が足りない学生が使う場合が多く見られました。
現行のテストに移行し、学力が評価基準の一端となるのであればギリギリまで受験勉強に手を出さない学生の受け皿として機能することはなくなるでしょう。
また、競争率が高くなるにつれて、当然望み通りにいかないことも考えられます。結果が分かってから一般選抜に切り替えるとしても、入試本番まで残り僅かです。受験勉強0からスタートでは間に合わない可能性が非常に高いです。あらゆる可能性に備えて一般対策も並行していくことが非常に重要です。
3.当塾での対策
3-1.現行試験への対策
~ 総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試を勝ち抜くための方法 ~
総合型選抜入試にしても、学校推薦型選抜入試にしても、高校1年次からの準備が不可欠です。 総合型選抜入試では希望大学のアドミッションポリシーに沿った人物とみられるよう学生生活を送ることが必要ですし、学校推薦型選抜入試では高校1年次からの評定の平均が必要となります。どちらも高校3年からでは対策しづらいものです。また、小論文もただの作文ではなく、相手を納得させる文章を書かなければなりません。このためには国語における論理的思考・構成力が必要となってきます。それは一朝一夕で養えるものではありません。
だからといって、決して高校3年次から始めて間に合わないというわけではありません(評定平均だけは取っておいてもらう必要がありますが)。ただ、早いうちに受験を意識すれば、対策を十分に立てられることは確かです。
さて、当つつじヶ丘個別学習会高校生教室では、毎年のように総合型選抜・学校推薦型選抜の指導を行っております。今年も指定校推薦の指導を行った生徒全員が、指定校推薦の校内選考を勝ち取っております。(詳しくは2024年度合格速報へ)
当塾で行っている主な対策は①定期試験対策、②小論文指導、③志望理由書指導、④面接対策です。
3-1-1.当塾の定期試験対策
一部の総合型選抜や学校推薦型選抜入試においては、評定平均がとても重要になってきます。当塾ではもちろんテストの範囲の対策を行いますが、それはその場しのぎの付け焼刃の対策ではありません。まずは受験基礎学力の養成です。テスト本番時のみ点が取れればいいというものではなく、大学入学後に勉強で苦労しないようにするためにも、土台となる基礎学力を身に付けた上で試験に臨んでほしいが故です。
冒頭で紹介しましたように近年は総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試で入学する生徒が増えている一方で、入学者の6人に1人が退学しているという現実もございます。そうならないためにも正しいやり方で勉強する習慣を身に付けて頂くという方針は、一般受験と変わりはありません。
まずは生徒一人一人の足りない部分を補い、そのうえで定期試験や受験の対策に当たっております。
3-1-2.当塾の小論文対策
いきなり小論文を毎日毎日書かせるのではなく、①でも申し上げたように、国語の基礎学力の養成から始めます。読解が中心となりますが、様々なジャンルの文章に触れることで本番においてどのような課題が出されても対応できるようにしております。
小論文添削では各々の志望校に合った出題形式(課題文型、テーマ型、図表読み取り型など)で演習を行っています。また、小論文ではその学科の特色に応じてかなり専門的な知識が要求されるものもあります。例えば医療系なら「インフォームドコンセントについてあなたの考えを述べよ」や、農業系なら「日本のエネルギー事情について述べよ」など、専門用語や背景となる知識がないと手も足も出ない問題が多々あります。そのような問題にも対応できるよう過去問の研究や対策に取り組んでおります。
3-1-3.当塾の志望理由書対策
志望理由書の作成に際して最も重視するのは、大学のアドミッションポリシーを理解したうえで書いているのかという点です。他にも構成力・表現等を誰が読んでも納得するまで徹底的に添削いたします。私たちが書く内容を指示するのは簡単ですが、あくまでも出願する本人の言葉を尊重して作成を行っていきます。
3-1-4.当塾の面接対策
各大学の面接内容が分かるものはもちろん、英語資格試験におけるスピーキング対策も行っております。
面接では当塾のスタッフが面談室を利用して1対1の面接指導を行います。予想質問やそれに対する応答の原稿作成まで、きめ細かく行います。スピーキング対策(主に英検)では語学が堪能であるスタッフが実際に行われる試験形式で質疑応答を行い、内容や発音などの改善を行います。
3-2.最後に
2020年度より実施される新試験への対策は、上記の従来のAO・推薦入試への対策に加えて、学科試験への対策も含まれます。大学側が大学入学共通テストを利用するのであれば、先行して実施された大学入学共通テストのプレテストの研究によって対策していくことは可能です。大学が独自のテストを用いるのであれば一般入試の対策と同様の対策を行っていくほかありません。
どちらにせよ、従来のような「3年生になってから」では間に合いません。当塾が理念の一部としている「基礎学力」がきちんと定着していれば、出願先の人気の状況で総合型選抜・学校推薦型選抜で万が一不合格でも一般試験で合格していけます。新試験は現行の入試に比べ実施期間が遅く、合否発表(12月)を見てから一般の対策はほぼ間に合いません。いかに早いスタートを切って起こりうる状況に対応していくかがカギとなります。
総合型選抜入試、学校推薦型選抜入試に向けてのご不明点、お悩み・ご相談等ございましたら、調布市にある個別指導塾、つつじヶ丘個別学習会にお気軽にお問い合わせ下さいますよう、お願い申し上げます。