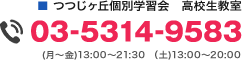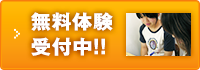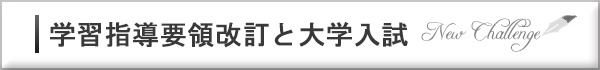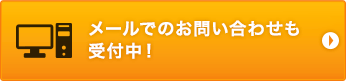英語4技能化とその対策
【目次】本記事は下記、大項目3部の構成になっております。
1.英語4技能化の背景
2.外部検定試験とCEFR
2-1.英語4技能
2-2.CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)
3.各技能に向けた当塾の対策
3-1.リーディングに向けた対策
3-2.リスニング・スピーキングに向けた対策
3-3.ライティングに向けた対策
1.英語4技能化の背景
以前から英語外部検定利用入試を導入している大学はありましたが、どちらかというと少数派でした。2020年度からの大学入試改革において、英語の試験は4技能を総合的に評価する方向性が決定し、国立大学受験では検定受検は必須となっていました。しかし、一転して英語4技能の評価を支援する英語成績提供システムの導入は見送られ全受験生が受検というわけではなくなりました。ただ英語外部検定利用入試を導入する大学は年々増加しておりますので、これからの大学入試の英語では「読む」「聞く」だけでなく、「書く」「話す」力が求められる、ということに変わりはありません。
これにはどういった背景があるのでしょうか。
急速なグローバル化の進展の中で、一人一人にとって、異文化理解や異文化コミュニケーションはますます重要になり、国際共通語である英語力の向上は日本の将来にとって極めて重要です。
東京オリンピック・パラリンピックを迎える2020(平成32)年はもとより、現在、学校で学ぶ児童生徒が卒業後に社会で活躍するであろう2050(平成62)年頃には、日本は、多文化・多言語・多民族の人たちが協調と競争する国際的な環境の中にあることが予想され、そうした中で、様々な社会的・職業的な場面において、外国語を用いたコミュニケーションを行う機会が格段に増えることが想定されます。
(文部科学省 今後の英語教育の改善・充実方策について 報告~グローバル化に対応した英語教育改革の五つの提言~ より引用)
上記引用の通り、入試改革のベースには英語力の向上、特に英語によるコミュニケーション能力の向上という目的があり、そのためには4技能化が必要不可欠であるということです。
また、英語に限らず教育改革の大きな流れを象徴する言葉のひとつとして、「思考力」というものがあります。この言葉の背景には、産業の機械化、もっと言えばAI化が進む未来において、社会の中に埋もれてしまわないような(端的に言えば機械にできない仕事ができる)力を身につけるべきだ、という意見があります。そのような時代にコミュニケーションは、人にしかできない仕事に必要とされる重要な能力であると共に、「思考力」を育てるためにも大切な役割を果たします。
つまり、コミュニケーション能力の向上は、相手の意図をくみ取る力、そして自分の意図を伝える力の育成につながります。そして、その二つの力をつなげる要素として、相手の意図を理解した上でどのように自分の意図を伝えるかという「思考力・判断力・表現力」があり、主要なアプローチの一つとして、コミュニケーションを通してそれらの力を育てられるからです。
このように、英語によるコミュニケーション能力の向上は、コミュニケーションの意識的な訓練になり、結果として上記3つの力の育成にもつながると考えております。
2.外部検定試験とCEFR
では、その4技能はどのように判断するのでしょうか。
以下、波線部から波線部までの『大学入試英語成績提供システム』を利用する内容は見送りとなっています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大学入試センターの発表では、
外国語科の科目のうち「英語」については、2020年度から2023年度までの枠組みとして、各大学は、センターが問題を作成し共通テストとして実施する試験と、民間の試験実施主体が実施する資格・検定試験とのいずれか又は双方を利用できることとされています。なお、センターが問題を作成する「英語」の試験については、「英語」以外の科目と同様に、高校教育を通じて大学教育の基礎として共通に求められる力を身に付けているかどうかを把握することが目的となります。具体的には「7」に示すとおり、義務教育段階の学習からの連続性を受けつつ「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英 語Ⅱ」「英語表現Ⅰ」の科目の範囲からの出題となり、CEFRとの対応ではA1~B1相当となる予定です。
一方で資格・検定試験は、試験の目的に応じて幅広い英語力を把握することが可能です。大学の判断により多様な結果が活用される可能性があることから、「大学入試英語成績提供システム」を通じて成績提供する範囲も A1~C2 の幅広い範囲が想定されているところです。
上記の通り、共通テストだけでなく外部検定試験を活用して4技能を判断することになるようです。
試験の目的に応じて幅広い英語力を把握する、とあることを踏まえると、新システム下では現在広がりつつある外部検定試験利用型の入試と同様に、大学側が利用する検定を指定してくる可能性がある、と考えられます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『大学入試英語成績提供システム』を利用して一元管理した4技能を参照する受験は見送りとなりましたが、2023年度の一般選抜では私立大学の約4割が英語外部検定利用入試を導入しており、年々増加傾向なことに変わりありません。
外部検定試験利用型入試および各検定試験の簡単な特徴については当塾でも以前に記事を書いております。
↓こちらのリンクより別記事が参照できます。
● 検定で優位に立とう! 英語外部検定を一般受験で評価する大学が急増中!!
● 大学入試の英語外部試験として採用されている検定試験の紹介
また、文部科学省の資格・検定試験 比較一覧表により詳しい情報が掲載されておりますので、興味のある方はご参照ください。
昨今、目まぐるしく変貌を遂げる大学受験において様々な変更が考えられるため必ず募集要項で確認する必要がありますが、「4技能を見る」という点は既定路線でしょう。ここで、改めて4技能について、およびCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)について理解しておきましょう。
2-1.英語4技能
まず、英語4技能の詳細を見ていきましょう。
英語4技能は、「リーディング(R)」、「ライティング(W)」、「リスニング(L)」、そして「スピーキング(S)」に分類される、英語を総合的に扱うための4つの技能を指します。
以前はリーディングのみ、つまり英語を理解する能力を対象として試験が行われることが多くありましたが、センター試験にリスニングが導入(2006年)され、TOEICでもスピーキング/ライティングテストが実施されるようになる(2007年)など、2000年代後半から4技能を総合的に判定する流れは続いており、英語技能の検定試験では4技能のそれぞれについて判定を行うものが主流となっていると言って差し支えないでしょう。
ただ、現状の大学入学共通テストにおいては、「読むこと」「聞くこと」の能力をバランスよく把握するため、筆記(リーディング。マーク式)とリスニング(マーク式)を課されています。内容に関してはCEFR を参考に、A1 から B1 までの問題を組み合わせて出題されています。また、実際のコミュニケーションを想定した明確な場面、目的、状況の設定を重視され広告やWebサイト、ブログ記事やレポートなどから文章が出題されています。
従来のセンター試験と科目としては同一の試験が行われています。ただし、筆記とリスニングが均等配点(いずれも100点満点)で実施されています。
2-2.CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)
CEFRを参考に、A1からB1までの問題を組み合わせての出題とは、どの程度のレベルを指すのでしょうか?
その前にCEFRとは何かを説明します。
CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)とは、ヨーロッパの全ての言語に適用できるような学習状況の評価や指導の方法を提供することを目的として設定された、外国語の学習者の学習状況を示す際に用いられるガイドラインです。
最も基礎の段階であるA1から、非常に習熟した段階であるC2までの計6つの段階があり、それぞれについて言語能力として何ができるかの基準が示されています。
様々な検定試験についても、CEFRと対照して、各検定のスコアによってCEFRのどの段階にあるのかが評価できるようになっているものが数多くあります。
更に、CEFR評価を経由することによって異なる検定間で評価の比較が可能になっています。
例えば、CEFR評価B1の下限がCSE2.0(新英検)だと1950(2級合格が1980)、GTEC / GTEC CBTだと960、TEAPだと225、TOEFL iBTだと42となっています。CEFRを基準として考えると、これらの点数が同じレベルとして評価されていることになります。
このCEFRにおいてA1~B1の範囲で出題する、ということです。では、B1の評価基準を以下に示します。
仕事、学校、娯楽などで普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば、主要な点を理解できる。その言葉が話されている地域にいるときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。身近な話題や個人的に関心のある話題について、筋の通った簡単な文章を作ることができる。
(文部科学省 資格・検定試験 比較一覧表 より引用)
と、文章だけでは少し理解の難しい面もありますが、日常の生活が不自由にならない程度の語学力が求められています。
3.各技能に向けた当塾の対策
では、英語4技能化に対応するために何をすればいいのでしょうか?
3-1.リーディングに向けた対策
読解には文法の理解が必須!
読解には精読も必須!!
4技能化への流れとともに、英語の文章読解は「長文化」の一途を辿っています。共通テスト、大学が作成した個別問題を問わず10年前と比べても圧倒的に長文が超長文になっています。長い文章を理解するためには読み慣れることも確かに必要です。ところが、英単語や文法が全く頭に入っていない状態では一向に超長文を読みこなすことはできません。きちんと読みこなすことができなければ、長文読解問題によくある「本文の内容と一致するものを一つ選べ」「傍線部を和訳せよ」「単語を意味の通る順に並べ替えよ」「空欄に適語を補充せよ」などの問題に対処することは困難です。
そこで文法事項の理解が必須となります。
そもそも各種検定や大学受験で、分からない単語が本文に出てくることがあります。分からない単語が出てくる場合の方が多いかもしれません。そこでどうするか。前後の文章理解や文法の知識を使って、時には推測しながら読んでいくのです。文の主要な構成要素であるS(主語)、V(動詞)をはじめとした文章の構成を分解し、構成要素同士の関係を見極める。そういった作業を経ることでこそ、構造を理解した上での解答ができ、安定した実力を発揮できるようになります。
また、文法だけに偏重することも良くありません。慣用表現、熟語や会話表現など、文法だけでは説明のできない記憶事項や、同一の単語に複数の意味を持つ多義語などを正しく見分けるには、それらを暗記するための涙ぐましい努力が必要となります。
我々は単に長文問題を解くだけでなく、精読をさせております。
精読は文章の内容を詳細に理解し、訳出ができることを目的の一つとします。後述いたします「基本文」とも通ずるところではありますが、この精読の演習を通じて英語の表現に対する理解を深め、頻出の英語表現と日本語の表現をリンクさせることができます。
当塾は決して文法をないがしろにせず、土台を着実に構築するとともに英語長文と対峙するよう心掛けております。
3-2.リスニング・スピーキングに向けた対策
話せずして聞くことは難しい!聞かずして話すことは難しい!
まずは単語から「聴き慣れよう」
4技能のうち、今まで各試験でも問われることの比較的少なかったものがスピーキングです。その判定の難しさから、導入されている試験はかつて少数でした。しかし現在ではインターネットの発展とともに遠隔でも会話ができるようになり、スピーキング能力を鍛える環境はかなり改善されてきました。とは言え、一般的にどこでもできるようになったとはまだまだ言えないのが現状でしょう。
リーディングのように本さえあればどこでも始められるものと違うので、スピーキングは少し取り掛かりにくいと思われがちです。また、気を付けてほしいのですが、スピーキングはリスニングとセットで練習しないと、会話のキャッチボールができませんし、捗りません。
まずはリスニング、聴くことに慣れるところから始めましょう。
最近は英語長文のテキストにCDやQRコードがついているものもあり、リスニングはスピーキングよりも容易に始められる環境が整っていますが、いきなり長文を聞いたところで、聴き慣れていない人は何やらよくわからない音の塊にしか聞こえない、そんなことがままあります。
そのため、長文を聞く前に、まずは単語を覚えるところから始めていきましょう。単語をアルファベットの並びだけでなく音とセットで理解しましょう。その際、聞いた後で必ず発声することです。聞いたことない音声を聞き取る、ましてや発声することはまず不可能でしょう。一つずつの単語を聞き取ることができて発音できることは最低条件です。例えば「you」と「are」を覚えていれば「ユー」「アー」は聞き取れるかもしれません。実際は英語にはリエゾンというものがあり、音が連結したりしますので、各単語の発音だけでは文章を聞き取ることは難しいでしょう。ただし、いきなりそのレベルにジャンプはできませんので、まずは各単語です。
そういった観点から、当塾では単語をしっかりと教室でチェックしております。受験直前の時期となりますとそうもいかない場合もございますが、口頭で英単語の発音をこちらで行いながら総当たりで意味のチェックを行っています。
また、英検の2次試験(面接)対策など、スピーキングを必要とする場面への演習・対策を行っております。英検(CSE2.0)のように、今後検定試験がそのスタイルを変更する可能性もございますので、各検定試験の動向も注視し、即応できるよう目を光らせております。(2024年度から英検はリニューアルされます。詳細はこちら)
3-3.ライティングに向けた対策
単語の継ぎ接ぎで作文は難しい!
フレーズを基本文で覚えよう
文法を理解し、単語や熟語を覚えたら文章が書けるようになるでしょうか? 答えはNoです。
ごく一部の特殊な例を除いて、知っているフレーズを応用する形で文章を組み立てることが一般的であると思います。そこで、私たちは文法学習の際に「基本文」の理解を同時に行います。
これにより、文法事項の理解とともにその文法を活用した「ベースとなる文章」を頭に入れてもらいます。そうすることによって、「そう言えば関係代名詞の単元で覚えた文章が使えそうかも」と思い出しながら文章を構成することができます。
一文の構成ができるようになったら、今度は文章を構成する段階に入ります。
例を挙げますと、英検2級でのライティング問題は提示されたテーマに対し80~100wordsで意見と理由を2つ書くことを要求されます。この文章量だと基本的には「意見→その理由①→理由②→結論」の順番で各パートを構成するのが常道でしょう。各パートで何を書けばいいのか等々、細かい注意点については割愛しますが、指定されるテーマや文章量によって書き方を考える必要はあるでしょう。そのような状況への対応も行っております。
これから4技能の習得を目指すみなさん、闇雲に勉強したのでは英語の迷路に迷い込んでしまいます。英語の学習に未来が見えない、どうにも自分ではやれそうにない、という方は是非当塾へお越しください。